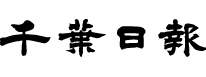2021年3月6日 14:00 | 有料記事
東日本大震災による津波などで死者14人(災害関連死1人含む)・行方不明者2人に及ぶ甚大な被害があった千葉県旭市は、「忘れられた被災地」とも呼ばれた。東北3県の被害ばかりを大きく取り上げるマスメディア。自分たちの街で何が起きたか分からなかった住民自身が立ち上がり、被災体験や復興の取り組みを伝える手作り新聞の発行を開始した。
それから10年。今もさまざまな活動が地元で続いている。昨今、高齢化や新型コロナ禍の影響も受けているが、自分たちの暮らす地域で起きた出来事や教訓を先につないでいこうという思いは変わらない。
(銚子・海匝支局 橋本ひとみ)
 過去の「復興かわら版」。温かみある似顔絵は楽しみにしてくれる取材相手もいるという
過去の「復興かわら版」。温かみある似顔絵は楽しみにしてくれる取材相手もいるという
知られていない被災地、その時
2011年3月11日、旭市は震度5強を観測し、午後5時25分すぎには最大高さ7・6メートルの大津波に見舞われた。海側中心の津波被害に加え、液状化被害も発生。避難所には一時約3千人が身を寄せた。市によると、全壊336世帯など住宅3828世帯に被害が出た。
「津波は繰り返し襲ってくる」。津波被害の大きかった飯岡地区に半世紀以上暮らす戸井穣さん(76)は震災後、市防災資料館の2014年開設に尽力。2月末に健康面などを理由に勇退するまで、館長として津波の脅威を伝えてきた。午後2時46分、自宅で過ごしていた戸井さんは「地球が終わるんじゃないか」という揺れの後、1キロ弱ほど離れた飯岡漁港に様子を見に行くと、底が見えるぐらいに水が引いていた。「これは大きい津波が来るぞ」
街の光景は一変した。近くの通りは海の方からトタン屋根の倉庫が押し寄せ、あらゆる家財道具やがれきが重なり泥砂も積もった。安否が気がかりだった近所の高齢女性が津波で亡くなり、心を痛めた。「火事場泥棒」に警戒し、夜はライトを手 ・・・
【残り 4123文字、写真 1 枚】