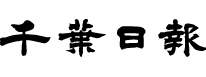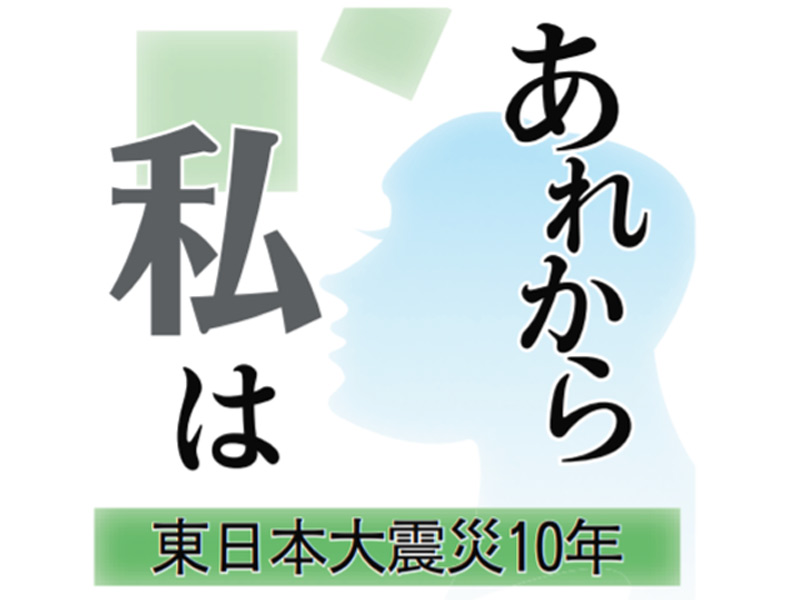
2011年3月11日、午後2時46分。日本上空にはこの日も多くの飛行機が飛んでいた。千葉県北部に位置する成田空港では、地震の影響で鉄道などの空港アクセスが寸断。約8500人の訪日客らが空港で夜を明かした。しかし闘いはこの後だった。福島原発事故による放射能漏れの影響を恐れ「一刻も早く帰りたい」と日本を脱出する在日外国人が殺到。夜中に被災地の外国人を乗せたバスが何台も連なって到着し、飛行機のチケットを手に入れるため空港に泊まり込む人は一時3800人にまで膨れ上がった。このとき浮き彫りになったのは「正しい情報発信」の重要性。震災以降も大雪や台風などの大規模災害に見舞われてきた10年間、日本の空の玄関口はどのような進化を遂げてきたのか。
(成田支局・今井慎也、デジタル編集部・山崎恵)
 震災当夜の成田空港旅客ターミナル=2011年3月11日
震災当夜の成田空港旅客ターミナル=2011年3月11日
巨大地震発生、その時国際空港は
10年前のあの日、日本航空グループ「JALスカイ」の地上係員、石山絵梨さん(37)は成田空港第2ターミナルの国際線カウンターで搭乗手続きの対応に当たっていた。期待に胸を膨らませて出発していく海外旅行客と笑顔で触れ合う空港のスタッフに憧れ、航空会社を目指した。
この日も多くの訪日客でターミナルはあふれていた。石山さんが台湾からの旅行者のパスポートを確認していたその時、大きな揺れに襲われた。カウンター頭上の案内モニターが激しく動いたのを見て、旅行者に離れるよう伝えると、パスポートや手荷物を残したまま屋外に避難する外国人もいた。ほかにも多くの人が屋外に避難する中、香港籍の車いす利用者が戸惑っていた。車いすを押して一緒に外に出て広い所に誘導したものの「そこから何をしていいのか分からなかった」。
すると、大勢の人がターミナルと一般道を結ぶ陸橋を歩いて移動を始めた。普段は乗用車しか通行できない道路だが、多くの人が広い駐車場を目指していた。
 ターミナルの外に避難する空港利用者ら=2011年3月11日(成田国際空港提供)
ターミナルの外に避難する空港利用者ら=2011年3月11日(成田国際空港提供)
石山さんら地上係員も駐車場に向かい、バス会社が開放してくれた車両に避難者を誘導する作業に当たった。シャツにベストの薄着だったことに気付き、3月の寒気が体を芯から冷やしていた。少しでも温まるよう係員同士で寄り添っていたところに、バス会社が空いている車両に招き入れてくれ、ようやく寒さをしのげた。石山さんは「お客さまを最優先は当たり前だが、自分の寒さも限界だった。バス会社の人の厚意に今でも感謝している」と振り返る。
原発事故の影響も直撃した。中国からきた救済便での出国者を始め、日本を脱出する訪日客の対応に追われた。日本では恐ろしいことが起きていると言う外国人をたくさん見送った。「私たちはここで仕事しているのに…」という複雑な気持ちもよぎった。
それから10年。石山さんはずっと成田空港でキャリアを重ねた。これまで経験したことのない規模の地震発生で何をすべきか分からなかった震災の経験から「いつ何が起きてもおかしくない」という意識が生まれた。社内外の訓練に取り組む真剣度が変わった。強風や台風で空港機能がまひした際も、滞留する外国人客に囲まれながら落ち着いて対応を説明できた。「震災で度胸がついた。お客さまを誘導できるのは、空港のことを知っている私たちスタッフだけ。何が正解か分からない時でも、しっかりしなくてはいけない」。
 10年間、成田空港でキャリアを重ねた「JALスカイ」の石山絵梨さん
10年間、成田空港でキャリアを重ねた「JALスカイ」の石山絵梨さん
風評被害を防げ 奔走した空港会社
震災当日、空港を運営 ・・・
【残り 3610文字】