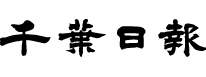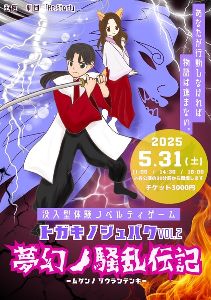近未来のデジタルコンテンツ技術が体験できる「デジタルコンテンツEXPO2013」が24~26日、東京都江東区の日本科学未来館で開かれている。コンピュータグラフィクス(CG)や仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、インタラクティブ技術などを活用した近い将来実用化されるかもしれない約40点の最先端技術が無料公開。ユニークな取り組みをいくつか紹介する。
◆スマホでうつ判定
まずはスマートフォン(スマホ)を使ってうつ病の傾向を自動判定できるアプリ「Utsukamo」。公立大学法人首都大学東京の大人プロジェクトチームが開発した。使い方は簡単。ユーザーの指先をスマホのカメラに当て、脈拍数を自動計測。雲が流れるリラックス映像を数分間見た後、再度脈拍数を計測すると、うつ傾向が判定される仕組みだ。
同チームによると、人はリラックスする映像を見ると副交感神経が活性化し、心拍変動指標であるHF値が上昇する。だが、うつ傾向の強い人はリラックスできず同値が下がったりするという。記者が体験したところHF値は316から902に上昇し「うつの傾向はありません」と測定された。担当者によると今回のイベント中デモを体験した数人がうつ判定となったという。
同技術は将来的にうつ病判定などへの応用が期待されている。
◆「アホ毛」を常に右跳ねに
次に紹介するのは東京大学・五十嵐研究室の「こだわり物理エンジン」。3次元CGアニメーションを「デフォルメ」(誇張表現)化するためのシミュレーションソフトだ。
従来の物理条件に忠実な物理演算エンジンでは、例えば女性キャラクターを正面から見た場合と横から見た場合では、当然髪型が異なって見える。アニメファンの間では「アホ毛」と呼ばれる触角のように跳ねた髪型は重要な外見的特徴なのだそうだが、従来のエンジンではどの角度から見ても「アホ毛」を常に右側に跳ねさせるといった物理条件に反した設定が難しかった。
そこで開発されたのがこの「こだわり物理エンジン」。一部の髪型を常に同じ角度で見せたり、横から見ても顔の表情が髪に隠れたりしないように“こだわり”を追加設定することができる。
開発を担当した同大学院修士課程の小山裕己さん(23)は「このエンジンを使うことで、アニメファンの満足感が高まる。オープソースになっているので、今後アニメやゲームを作るアーティストの人たちに活用してもらいたい」と普及に期待した。
◆テンセグリティ建築
千葉大学大学院・平沢研究室の「ARで建築施工支援」は、「テンセグリティ」と呼ばれる構造体を使った建築の施工支援に拡張現実(AR)技術を利用している。
入り組んだ多面体的な構造を持つ「テンセグリティ」は、オブジェなどの芸術表現として使われてきたが、学生たちはこれを工学的に応用しようと挑戦。アルミパイプとステンレスワイヤを立体パズルのように組み合わせた構造体を軽量建築として実用化できないか模索している。イベント会場には小規模版を持ち込んだが、研究室には縦横3メートルの屋根が設置してあるという。
問題は、構造が複雑なため、設計データ通りに部材が組み立てられているかどうかの検証が必要だということ。そこで、携帯端末で拡張現実を表示し、データと組み立てたものの3次元位置情報を重ね合わせて誤差を確認する施工管理技術を開発した。
実用化前の同技術だが、同大博士課程の飯村健司さん(28)は「テンセグリティは浮遊感を表現できるので、ドームなど大空間で生かせれば」と話した。