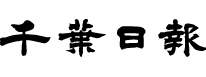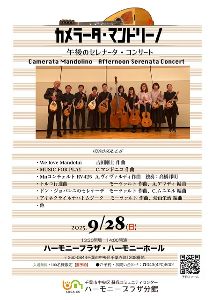2025年3月1日 17:10 | 無料公開

佐紀池ノ尻古墳跡(丸印)が見つかった奈良市の佐紀古墳群
奈良市の佐紀古墳群で、奈良時代の都だった平城京造営の際に破壊されたとみられる全長約200メートルの巨大前方後円墳の痕跡が見つかり、1日、奈良市が発表した。佐紀池ノ尻古墳と名付けた。市によると、平城京内では約30カ所で古墳が壊されているという。
市によると、200メートル以上の古墳は全国で約40基あるが担当の村瀬陸学芸員は「完全に消滅した全長200メートルもの古墳が見つかるのは全国初。古墳の規模から王権中枢を担った人物だろう」と話した。
佐紀古墳群は4〜5世紀にかけて奈良市北部に築かれており、成務天皇陵や神功皇后陵がある。巨大古墳の集中地域が奈良から大阪へ移る過渡期の大王クラスらの墓とみられている。
陵墓参考地・コナベ古墳(前方後円墳)のすぐ南側で発見。平城京の区域内に当たるため造営時に破壊されたらしい。
2023年の発掘で、古墳周濠とみられる溝を発見、4世紀末のひれ付き盾形埴輪の破片が出土した。これまでに奈良文化財研究所(同市)による発掘でも古墳の存在が指摘されていた。